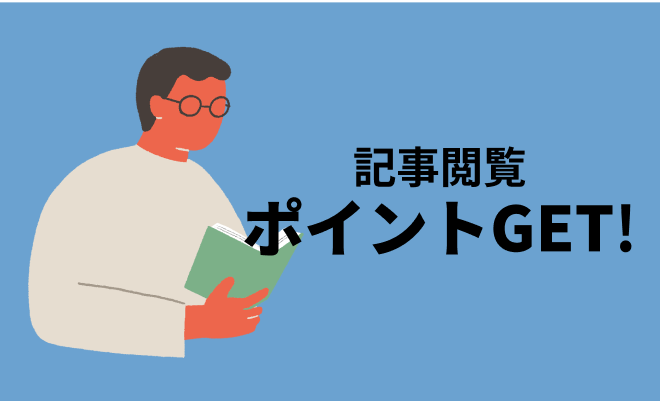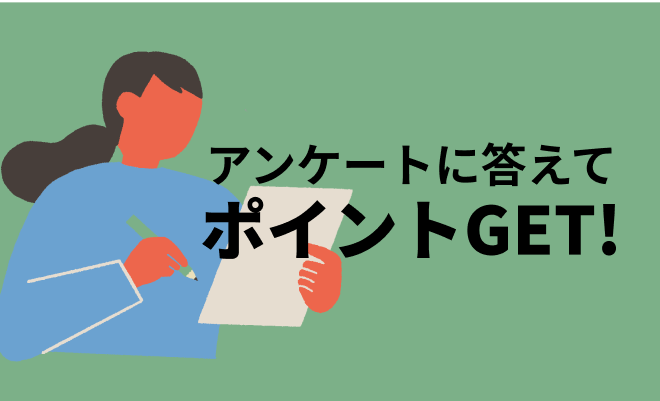いま、全国的に問題になっている保育士不足。
滋賀県も例外ではなく、保育士不足の影響で受け入れる子どもの数を減らさざるを得ない保育所等が増えた結果、2024年4月には待機児童の数が全国で3番目に多くなっています。
そんな中、現場で働く保育士さんたちはどのような思いで日々子どもたちと向き合っているのでしょうか?大津市にある「風の子保育園(穴太福祉会)」を訪問し、現場のリアルな声を聞いてきました。
先生だって支えが必要!みんなでつくる働きやすい保育園

風の子保育園は、大津市にある認可保育園。設立から50年を迎えた歴史ある園で、0歳から5歳までの約170人の子どもたちを受け入れています。
朝から元気いっぱいの子どもたちの声が響く中、「おはようございます!」と笑顔で迎えてくれたのは田中先生。

「保育士の仕事で嬉しいのは、子どもたちからたくさんの元気をもらえることです。自分がしんどいときでも子どもたちは笑顔で迎えてくれて、時にはギュッと抱きしめてくれるんです。こちらが励まされることも本当にたくさんありますよ」

その一方で、やはり大変なことも。
「人手不足が大きな課題です。そのため最近では、中学生や高校生向けの職場体験を通して保育の魅力を伝える取組をしています。実際に体験すると『子どもと関わる仕事って楽しい!』と感じてくれる人も多いので、この仕事の楽しさを知ってもらえたらいいなと思っています」
最後に「長年この仕事を続けてこられたのは、支えてくれる仲間や家族の存在があったから」と話してくれた田中先生。周りの支えが保育士さんの力になって、子どもたちの笑顔をつくっているんですね!

続いては、園内を案内しながらこの仕事のやりがいについて話してくれた福井先生。
「一番のやりがいは、子どもたちの成長を間近で感じられること。最初は泣いてばかりいた子が、ある日『ありがとう』と言ってくれたときは本当に感動しました。子どもは一人ひとり違うので、その子に合った関わり方を考えるのが大事。『この先生といると楽しい』『安心できる』と思ってもらえるように、寄り添いながら保育をしています」

「最近は男性保育士同士の交流や、研修の機会も増えてきました。たとえば運動を取り入れた遊びを新しく学んだり、『こういう時ってどうしてる?』といった意見交換ができたりしてすごくありがたいです。時間内に仕事が終わらない日もあって、まだまだ課題は多いですが、少しずつ働きやすい環境が整ってきていると思います」
風の子保育園では、現在3人の男性保育士さんが働いています。男性・女性を問わずさまざまな大人と接することで、子どもたちの遊びやコミュニケーションの幅も広がりそうです!
最後に、働きやすい環境づくりについて、園長の長尾先生に聞いてみました。

「私たちの園では、職員の業務負担を減らすために『ノンコンタクトタイム』を導入しています。これは保育士が子どもと離れて、書類作りなどに専念できる時間をつくること。気持ちの切り替えや、残業時間の短縮に効果があればと思って始めた取組です」

「また、休憩時間をしっかり取れるように職員専用の休憩室も設けました。先生同士で話をしたり、一人で静かに過ごしたりすることで、仕事の疲れを軽減できるようにしています。最近は政府や自治体からの補助が手厚くなり、保育士の給与も以前よりは良くなってきました。現場の先生たちが主体的に考え、得意なことを活かしながら働ける運営を大切にしています」
給与面に課題があり、勤務時間が長いと思われがちな保育の仕事ですが、それぞれの園の取組や業務負担を減らす工夫が進み、働きやすい環境が整えられています。
保育士を応援する滋賀県の取組

とはいえ、「待機児童数が全国3位」というのは深刻な問題。
三日月知事も、「待機児童の解消には、保育人材の確保・定着が重要で、必要不可欠だと思います。保育士の方々の業務を軽減するための業務ICTシステムの導入促進、潜在保育士の職場復帰支援など、まだまだできることがある」と述べ、さまざまな支援を進めています。
そのひとつが、滋賀県保育士・保育所支援センターの取組です。

たとえば「保育の仕事出前講座」では、高校生や大学生を対象に就業継続支援アドバイザーと現役の保育士が学校を訪れ、仕事の魅力ややりがいを伝えています。「お話を聞いて保育士になりたい気持ちが高まりました」と好評で、学校側からもオファーの多い取組です。
また、「保育人材バンク」では、保育経験の豊富なアドバイザーや再就職支援コーディネーターが求職者一人ひとりに合った保育所やこども園を紹介し、就職までをサポート。特にブランクがある潜在保育士の方にとって、再就職の心強い味方になっています。

他にも「再就職支援研修」や「園見学会」、「出張相談会」など、保育士として復帰したい方から保育の仕事に興味がある方までサポートする、さまざまな事業が実施されています。
さらには、養成学校に通う学生向けの「保育士修学資金貸付」や、潜在保育士のみなさんの復職時の費用負担を軽くする「就職準備金貸付」や「保育料の一部貸付」といった貸付金のサポートも。一定の条件を満たせば返済が免除される制度もあり、多くの人が利用しています。また、滋賀県独自の制度として「奨学金の返還支援」も実施されています。
子どもが安心して育ち、保育士さんが安心して働ける環境をつくるために、滋賀県はこれからも取組を進めていきます!
みんなで支えよう!子どもの未来と保育の現場

保育士さんは、子どもたちの成長を支えるとても大切な存在。「先生、大好き!」「ありがとう!」 子どもたちの元気な声が飛び交う園内には、笑顔があふれています。
滋賀県では子どもたちがのびのびと育つための環境づくりを進めています。
保育の充実を目指すべく「保育人材確保対策」を進めるほか「病児・病後児保育事業」として、病気の時に安心して預けられるサービスにも力を入れています。「放課後児童クラブ支援事業」では、子どもの居場所づくりを行い共働き家庭をサポート。地域全体を巻き込んだ取組もあります。
また、子どもたち自身の声を社会に反映する「子ども県議会」や「子どもの貧困対策」に加えて、将来の選択肢を広げるためのデジタル教育や特別支援教育、農業体験や美術館などの活用も強化しています。
すべての子どもが安心して成長できる社会を目指し、滋賀県ではさまざまな学びの機会をこれからも提供していきます。
(文・林由佳里/写真・辻村耕司/編集・しがトコ編集部)