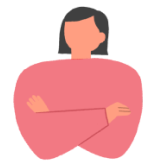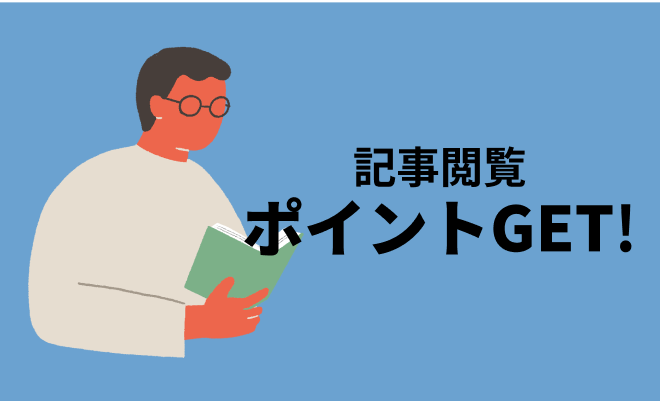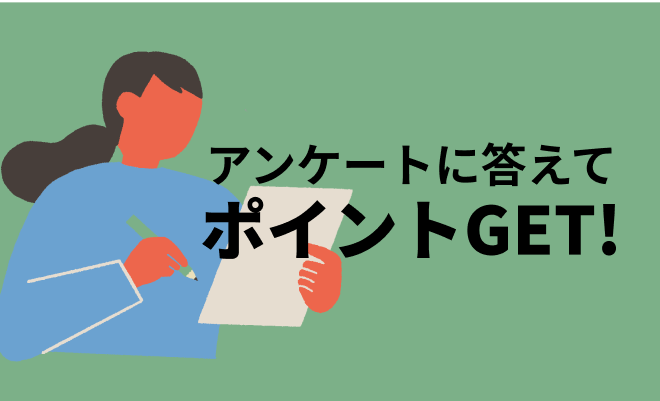みなさんは信楽焼というと、何を思い浮かべますか?
たぬきの置物が有名ですが、じつは信楽焼はもう一つの大きな特徴があります。それが「大物づくり」の産地であるということ。横幅が30cm以上、時には1メートルを超える大きなものを作ることができるのが、信楽焼の大きな特徴です。
1970年の大阪万博のシンボル「太陽の塔」の背中にある「黒い太陽」も信楽産。当時から信楽が得意としていた技術に岡本太郎が目をつけ、3000〜4000個ものタイルを信楽焼で作ったそう。
ほかにも、時代の流れに沿って暮らしに欠かせない大物を生産し、豊かになっていく日本を陰で支えてきた信楽焼。今回は、そんな信楽焼の土台ともいえる“産業”としての一面に迫ります。
何でも作る!転んでも起き上がる信楽のパワー

信楽焼の歴史は鎌倉時代までさかのぼります。すり鉢や水瓶など、生活に欠かせない道具を作ってきました。
江戸時代から昭和にかけては火鉢の生産がピークに。なんと、日本中の火鉢の8〜9割が信楽製だったとか!登り窯を100基フル稼働させても追いつかないほどの人気ぶりでした。

こちらは世界遺産「富岡製糸場」で使われていた糸取鍋。金属製だとサビや化学変化で絹に色がついてしまうため、信楽焼の鍋が大活躍しました。
しかし、時代は移り変わり、昭和30年代には石油ストーブの普及で火鉢の需要が激減。ピンチを乗り越えるため、観葉植物ブームに乗って作った植木鉢が大ヒット!しかし、プラスチック製品の台頭で需要が低迷。そこで信楽は洗面ボウルや浴槽などのインテリア分野に新たな活路を見いだしました。

「信楽焼といえばたぬきの置物?」と思うかもしれませんが、じつは売り上げのわずか3パーセント。信楽は時代の波に何度も揉まれながら、そのたびに新しいものづくりに挑戦してきたのです!
ここがすごい!信楽焼の「大物づくり」の秘密

では、どうして信楽は大きなものづくりが得意なのでしょうか?その秘密を探るため、「信楽窯業技術試験場」を訪ねました。

迎えてくれたのは、場長の高畑宏亮さん。
「信楽で大物づくりが発展したのは、まず土に秘密があります。信楽の土は縮みにくく、耐火性が高いんです。焼きものは焼くときにどうしても縮みますが、その縮みが大きいと割れてしまう。でも信楽の土なら大丈夫なんです」
信楽の土は、かつて琵琶湖の底だった地層から採れる特別なものだと言われています。だからこそ、大物づくりが可能なんですね!
「さらに、『大物ロクロ』の技術を持つ職人がいるのは全国でも信楽だけなんです」と高畑さん。火鉢から植木鉢、傘立て、そしてインテリアへ。信楽は独自の技術で時代のニーズに応えてきました。

試験場では、焼きものを学ぶ研修生たちが「大物ロクロ」「小物ロクロ」「素地・釉薬」「デザイン」の各コースで腕を磨いています。
今年の春から研修に通う水野さんは、「大学では全然違うことを学んでいましたが、陶芸に惹かれてここに来ました。同じ形を作るのは難しいけど、それがまた楽しいんです」と笑顔で語ります。

大物ロクロの技術を学べる試験場は、全国でここだけ。一人前になるには多くの経験などが必要ですが、その分やりがいも大きなものがあります。
ロクロで浴槽⁈ 世界で輝く信楽の技術
では、大物ロクロでは実際に何を作っているんでしょう。そこで、同じく信楽で大物陶器を手がける「株式会社陶器屋」さんを訪ねました。

「これが信楽焼で作った浴槽です。人がすっぽり入る大きさで、存在感バツグンでしょ」
出迎えてくれたのは、社長でもある、伝統工芸士の髙原誠治さん。高原さんも試験場の卒業生です。
「せっかくなので、作ってるところも見ていってください」

この大きな円の台座が、大型ロクロ。まずは大量の粘土を積み上げ、ロクロを回しながら、形を整えていきます。

ある程度積み上げたら、ロクロを回して表面を滑らかに整えていきます。全体のバランスや立ち上がりの角度に注意しながら、柔らかい粘土を成形していきます。成形の見本があるわけでもなく、手の感覚をもとに進める作業。まさに、経験がものをいう職人技です。
「重い粘土を扱うので、けっこう体力勝負なんですよ。でも、一つひとつの作業は集中力も必要です。大変そうに見えるかもしれませんが、でも、それ以上に楽しいですよ」と髙原さん。そこには、伝統工芸士としての情熱が感じられます。

形ができたら、あとはガス窯で7日間ほど焼き上げ完成です。高級旅館やサウナ施設など、全国はもちろん世界中で使われています。陶器の浴槽といえば、ほぼ信楽焼なんだとか!
「昔から、『大物を制する者は信楽を制する』と教えられてきましたが、まさに信楽焼の特徴がここに詰まってます。浴槽は、昔から需要が安定していましたが、この数年でさらに注文が増えてきてます。ものづくりに興味がある若い人には、ぜひこの世界に飛び込んできてほしいですね」と髙原さんは話してくれました。
地場産業を知って、未来をつくろう!

信楽窯業技術試験場では、令和7年度の研修生を募集しています。未経験でも大歓迎!滋賀が誇る伝統技術を身につけて、あなたも職人の道を歩んでみませんか?
じつは滋賀県には信楽焼を含め、9つの地場産業があります(長浜縮緬、彦根バルブ、彦根仏壇、彦根ファンデーション、湖東麻織物、甲賀・日野製薬、信楽陶器、高島綿織物、高島扇骨)。2024年4月からは滋賀県へのふるさと納税の使い道として「近江の地場産業と伝統的工芸品を応援」が選べるようになりました。
職人の道を目指すのもよし、職人を応援するのもよし。滋賀ならではの地場産業、ぜひ注目してみてくださいね!
令和7年度 滋賀県窯業技術者養成研修 研修生募集
受付期間:令和7年1月7日(火)から 1月24日(金)まで
試験日時:令和7年2月5日(水) 午前9時から
(文・林由佳里/撮影・出原敬介/編集・しがトコ編集部)