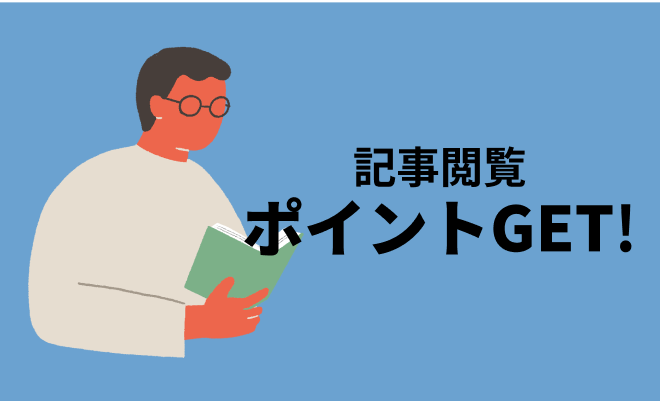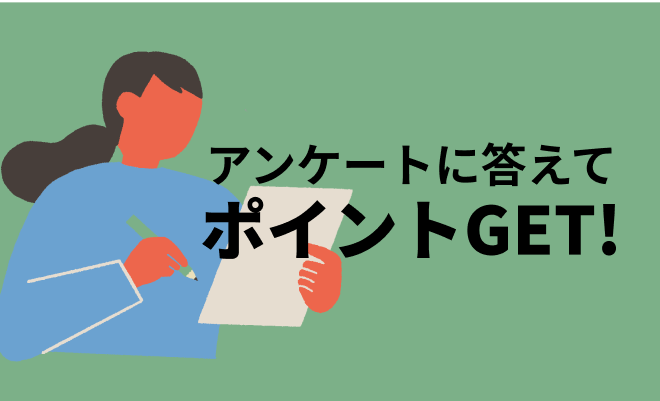明治のはじめ、琵琶湖の水を京都へと運ぶために作られた「琵琶湖疏水施設」の一部が国宝に指定されることになりました。明治時代の土木遺産が国宝になるのは、日本で初めてのこと。しかも、いまも現役で水を運び、船で観光もできるという特別な“水の道”。
そんな琵琶湖疏水を体感するため、5月30日、三日月滋賀県知事・松井京都市長・佐藤大津市長が「びわ湖疏水船」に乗船し、疏水の歴史と魅力を再確認しました。
日本の近代化を支えた“水の道”
琵琶湖疏水が建設されたのは、明治時代。
東京への事実上の遷都で活気を失っていた京都を復活させるため、滋賀県大津市から京都市へと琵琶湖の水を引く壮大なプロジェクトが始まりました。
完成した第一疏水は全長約20km。当時日本最長だった全長2,436mのトンネル「第一隧道(ずいどう)」や、琵琶湖と疏水の水位差を調節する「大津閘門(こうもん)」、疏水の水量調節を行う「堰門(せきもん)」など、革新的な技術が数多く取り入れられました。
この疏水によって、京都では飲み水はもちろん、日本初の一般供給用水力発電所の稼働や、物資の輸送、農業用水など、多方面に活用されるように。まさに日本の近代化を支えた“希望の水路”だったのです。
船上で間近に感じる、歴史と技術の結晶
当日は、三井寺乗下船場(大津)から蹴上乗下船場(京都)までをびわ湖疏水船で移動。船上では、学芸員による解説も行われ、明治の土木技術と今に残る遺産の魅力に触れる時間となりました。
下船後、三日月知事は、「琵琶湖の水の恵みや、琵琶湖疏水の存在は、改めて世界に誇れるもの。国宝指定は私たちにとって大きな誇りであり喜びです。びわ湖疏水船に乗って、その歴史や価値が体感できることを多くの人に伝えたいと思っています」と話しました。
今も現役で活躍する琵琶湖疏水は、“生きている文化財”。その価値を未来へと受け継いでいきたいですね。
(文・山田明日香/写真・東田七星/編集・しがトコ編集部/動画編集・大塚慎也)