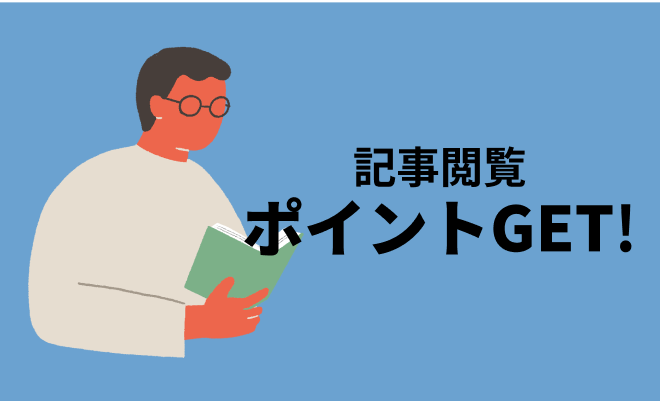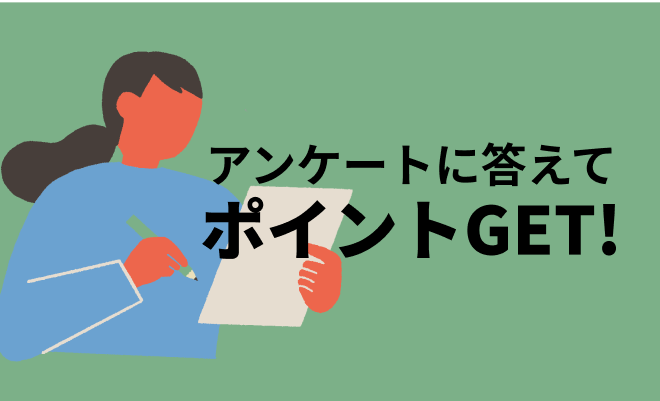滋賀県豊郷町にある「龍ケ池揚水機場」が、世界かんがい施設遺産に登録!
世界かんがい遺産への登録は、滋賀県初。さらに、地下水を利用した機械構造物として登録されたのは日本初の快挙。
そんな貴重な施設ですが、実際にどういう役割を果たしたのでしょう。滋賀県豊郷町へ取材に行ってきました。
明治42年の大干ばつから始まる建設計画
日本一の湖・琵琶湖を中心とした滋賀県は、歴史的に水との共生が重要なテーマ。なかでも、豊郷町を含む湖東地域は、水源確保の困難さが人々の生活を脅かしていました。そんな中で起こった、1909年(明治42年)の大干ばつ。40日間も雨が降らないなど、その被害は豊郷でも深刻でした。そこで、地域の人々が団結して計画したのが、この「龍ケ池揚水機場」。干ばつに苦しむ農地に水を供給するため、動力で地下水を汲み上げるという、当時とても画期的な施設でした。
建設に至るまでの道のりは険しいものでした。この当時、地域の人々は「お番水」や「はねつるべ」といった手法で川や小さな池の水を確保していました。「お番水」というのは、少量の水源を厳格なルールの下で分け合うきまり。「はねつるべ」とは、干ばつの際に野井戸からわずかな水を汲み上げる命を懸けた労働作業。いずれも村人への負担が大きいものでした。こうした状況を打破すべく、地下水を汲み上げるための建設計画が決断されました。
建設は大干ばつのあった年の12月から開始され、深さ11メートルに及ぶ掘削は、村人総出の手作業によって行われました。当時世界三大ポンプといわれた高価なイギリス製のポンプも導入。完成したのは、4年後の1913年(大正2年)でした。
地域を支える「龍ケ池揚水機場」
「龍ケ池揚水機場」が出来たことにより、豊郷の暮らしは大きく変わっていきます。田畑に水が安定供給されることにより、農作物の収穫量が安定化。さらに、重労働から解放された村人たちは、新たな産業や副業に取り組むことが可能になりました。養蚕や麻織物の生産が活性化し、二毛作も行われるようになります。伊藤忠兵衛を輩出するなど、近江商人の町として知られる豊郷町で、商業と農業の両輪が動き出します。龍ケ池揚水機場は地域の生活を支え、経済の発展に寄与していくのでした。「龍ケ池揚水機場」には、雨井神社という神社も併設されています。ここは、単なる水の汲み上げ所ではなく、水を守る、水と生きる人々の心の拠り所でもあったのかもしれません。
現在、龍ケ池揚水機場は、令和2年の故障以降、稼働はしていません。当時の工事の記録や資料をもとにその歴史的意義が再評価されたことにより、再稼働への期待が高まっており、修理に向けた検討が進められています。今回の「世界かんがい施設遺産」への登録が、地域の誇りとして新たな注目を集める機会となりそうです。
お話を伺った豊郷町学芸員の加藤さんは
「ここから動力を用いた地下水利用という灌漑技術が全国に広まっていったということを、もっとたくさんの方に知ってもらいたいですね」と話してくださいました。
(文・林正隆/編集・しがトコ編集部/動画編集・大塚慎也)